2年後には実際にプログラミングを授業の中で実施しなくてはなりません。
有難いことに、学校設定科目として3年生に情報演習の授業があります。
今年度から、実験的にプログラミング授業を行うことにしました。
その2時間目の内容を実践したところで、少し脱線してみました。

この段階では、body内にはJavaScriptに関わる特別なタグの記述はありません。
アラートを繰り返し処理をして連続表示させます。
JavaScriptの記述
ここから変えていきます。
最初の状態だとアラートの中身は
alert(“こんにちは!”);
になっています。
こいつが5回出てくる状態です。
ここで演習とします
- 「こんにちは!」の表示を「0」「1」「2」が順に表示されるように変更しなさい。
- 「0」を飛ばして、「1」「2」が順に表示されるように変更しなさい。
これでfor文の中身の動きを理解をするには十分ではないでしょうか。
1つ目は、「”こんにちは!”」を「i」に変更すればいいですね。
「” ”」が文字を利用する際に有効で、変数等では不要であることを理解します。
2つ目は、「let i = 0」の初期値を「let i = 1」に変更すればいいですね。
初期値の設定がどこに生きているかを理解します。
初期値を「0」に設定しているので「0」「1」「2」の3つの数字が出てくること、「i < 3」の範囲ということは「3」は含まれないことがポイントです。
検討事項
様子を見ていると、生徒は以下のように考えている子が半数いました。
alert(“0”); alert(“1”); alert(“2”);
たしかに出てはきます。
が、これではfor文の意味がまるでありません。
100回繰り替えすならどうする?なんて話をします。
なおかつ、全部で3行で済むよ。なんてヒントを出すと、進められる子が出てきます。
すごく簡単なことをやっていますが、この辺りの理解を深めるところから始めたいです。
が、完全に共通テストの予想問題には届きません。
今後はそのあたりまで見据えてカリキュラムを考えなくてはいけません。
が、現状はこの辺りで右往左往しているのが現実でした。

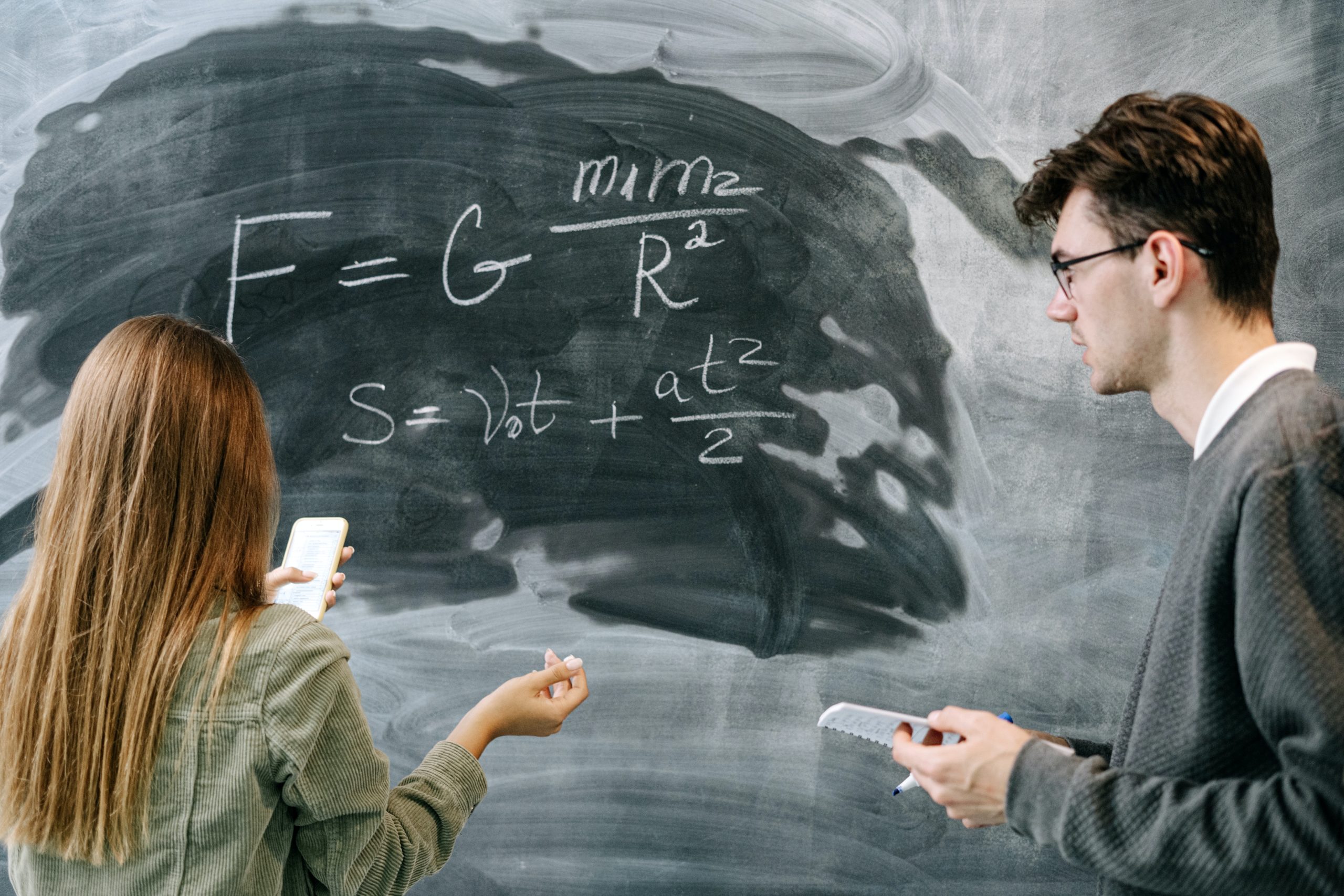


コメント